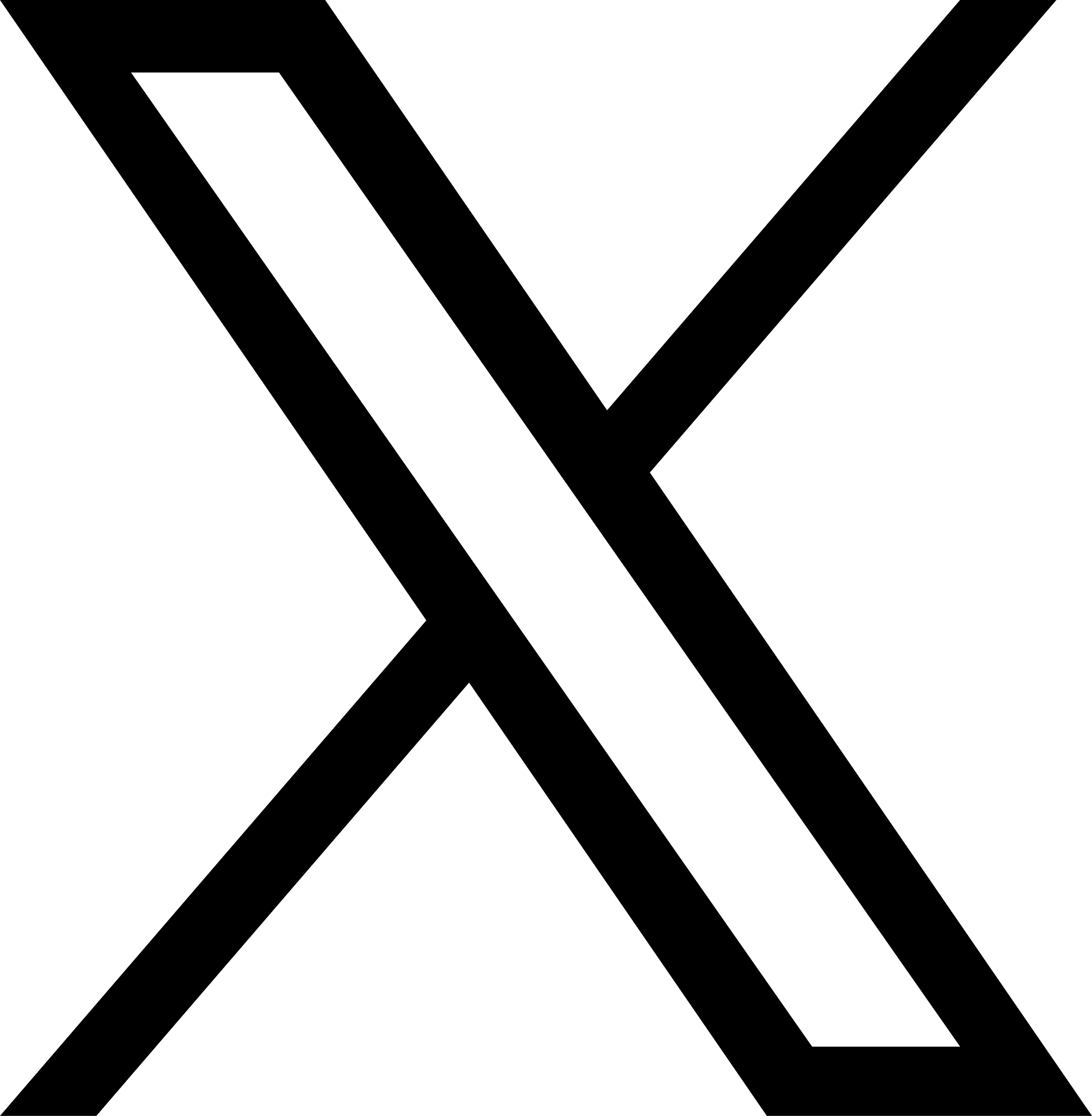シェルターでの動物の幸せを考える医療
 アメリカではペットの処分理由のNo.1がシェルターへの持込。
アメリカではペットの処分理由のNo.1がシェルターへの持込。
そんな現状を回避すべく近年誕生した「シェルターメディシン」。
その学問の根底にあるのは 「シェルターの動物を医療面から分析し 現状を改善することで新しい飼い主さんを早く見つけたい」、 そんな『優しい気持ち』でした。
この研究の第一人者である田中亜紀先生が日本に帰国中、 貴重なお時間を頂戴してアニドネスタッフがお話をお伺いしました。(2012年7月取材)
Profile
 |
Aki Tanaka/1974年生まれ 日本獣医生命科学大学卒業 獣医師 2001年渡米 カルフォルニア州立大学デイビス校にて、 Department of Environmental ToxicologyのMaster’s course修了 その後、同大学でMaster of Preventive Veterinary Madicineをシェルターメディシンで修了 現在、Department of EpidemiologyでPhD(博士課程) 日本獣医生命科学大学の非常勤講師を務める 新潟国際ペットワールド専門学校 特別教師 日本の4か所の自治体と協同で動物群動態と感染症の発生状況や疫学的分析を実施 Department of Environmental ToxicologyのMaster’s course修了 |
―日本では聞き慣れない「シェルターメディシン」について教えてください。
 「アメリカでも近年やっと学術的な分野として認められたばかりのシェルターメディシンは、2001年に私が所属するカルフォ ルニア州立大学デイビス校で研究が始まりました。
「アメリカでも近年やっと学術的な分野として認められたばかりのシェルターメディシンは、2001年に私が所属するカルフォ ルニア州立大学デイビス校で研究が始まりました。
まだまだ新しい学術分野ですね。
そもそも、なぜ研究する必要があったのかを説明しますと、アメリカでのペットの処分理由のNo1がシェルターでの殺処分だったんです。
アメリカでもペットは家族同然の位置付けですが、約20%のペットがシェルターに持ち込まれる現状がありました。
そのシェルターではやはり処分することがメインでしたが徐々に次の里親を見つけるという風潮に変わっていくとともに、動物が集団で過ごすシェルターでの管理状況によって動物の状態が大きく変わることが判り、ベストな方法を見つけるために研究が始まりました。
今では、コーネル大学、フロリダ大学、コロラド大学等にも学部が設けられる分野となり、獣医学生やシェルターワークに 関わる人間であるなら周知の学問となりました。
獣医医療内容としては、一般のペットですと、その個体だけの健康管理になります。
ですがシェルターでは、多くの動物がおり環境がまったく異なります。
その中でシェルターメディシンの目的は『群の健康を維持し心身ともに健康な動物を1頭でも多く譲渡すること』なんです。
よって、研究範囲は多岐に及びます。
動物種による適切な管理方法、疾患の状態による群管理医療、管理するスタッフの効率的な運用の仕方等々。
一例をあげますと、猫をレスキューしたとします。
その猫を管理する際に、犬が多くいる部屋で過ごしたとしたら、個体によっては恐怖やストレスによって食欲が落ち免疫が 低下し鼻気管炎等の疾患を発生する確率が高くなります。
その疾患が感染性だった場合、他の健康な動物にも伝染してしまう、その結果、譲渡率が低下する結果となってしまう、こういったリスクを極力少なくするのがシェルターメディシンなんです。
ですから、新しくシェルターを建築する際に相談に乗ることも多いですね。
例えば、空調の配置や換気状況によって感染症の発症率は大きく異なる実証が出ています。
また、動物行動学面からのアドバイスも重要で、猫のケージ内には必ず隠れる場所があったほうがストレスなく過ごせる、 上下に動けるような造りにする等を考慮しているかどうかによって、そこで過ごす動物の状態は大きく異なるのです。
シェルターメディシンは、どうしても感情移入をしやすい分野です。
ですが、データをもとに正しく解析し、客観的に判断することが何より重要だと考えています」
―なぜ、田中先生はこの分野の研究をしているのでしょうか。
「そうですね。私は中学生までイギリスで育ちました。
イギリスでは、学校にRSPCA(王立動物虐待防止協会)やブリーダーの方が来て、動物がいかに素晴らしいか、人間と一緒に築いてきた歴史、また正しい飼い方等を教えてくれるんですね。
家庭ではシェルターに行き、ペットをもらい受けるのは当たり前でした。
日本に帰国後、あまりに事情が違うことに大変に驚き興味を持ちました。
獣医学生だったころもイギリスに行ってはシェルターでボランティアをしてましたね。
とにかく、何が違うのかどうしてなのか、興味があったんでしょうね。
そして、カルフォルニア州立大学で研究を始めたのち、同校にてシェルターメディシンの学部が開設されることになり迷わず希望し、現在の研究に至っています。」
―日本とアメリカにおける、シェルターワークの違いを教えてください。

「これは、日本のみなさんは勘違いされていることが多いのですが、シェルターの施設のハード面は日本とあまり変わりません。
もちろん、アメリカのほんのいくつかの施設は、資金もスタッフも潤沢にありすばらしい設備を持っています。
でも、それはほんの一部。
他の施設は、古い造りが多く日本の愛護センター等とさほぼ変わりせん。
ただ違うのが、シェルターメディシンという概念が定着していること、あとはシェルターを管理するソフトを必ず導入していること、そしてボランティアスタッフの管理の仕組みが出来上がっている、その3点が大きく異なると感じています。
特にシェルターを管理するソフトウェアは、毎月の使用料が高額にも関わらずどんな小さなシェルターでも活用しています。
ソフトで管理する内容の一例をあげると、譲渡・引き取り、ワクチン接種の有無、安楽死の頭数および発生理由、シェルター内での疾患の発生率と罹患率、平均滞在日数、譲渡後の出戻りの頻度と理由、ボランティアの管理等。
常に動物の状態を数値化して管理する仕組みができあがっています。
実は、この管理ソフトですが、富士通さんにご協力いただきながら現在開発中なんです。
まだ、世に出ておりませんが、今後日本で広まり、シェルターワークの下支えになることを大きく期待しています。
また、アメリカのシェルターは、キルシェルターやノーキルシェルター、ローキルシェルターが混在しています。
とにかく広い国ですから州によって管理する動物種も異なります。
野生動物も多いですしね。
さまざまなシェルターが役割分担をしている、そんな状況でしょうね」
―今後、どのような活動をしていかれるのでしょうか。
「そうですね、私の希望としては、あと数年で日本に帰ってきたいと思っています。
現在、年に2回は帰国しながら、日本の行政に協力してもらいシェルターでの動物群管理と感染症の発生状況や疫学的分析を重ねています。
帰国後は、いまより現況がよくなるよう、今までの研究の成果を生かしていければと考えています。
シェルターメディシンは、新しい学術分野です。
私は数少ない研究者です。
動物がかわいそうだから救いたい、という気持ちも大切ですが、学術的見地から現状を変えることができれば、より大きな成果が生まれると確信しています。
毎回日本で行う勉強会は、座席が足りなくなるほど好評です。
来られる方は行政(保健所や愛護センター)や動物愛護団体の方、獣医師等です。
みなさん、とても熱心に講義を聴きなんとか現状をいい方向へと変えようとしていることをひしひしと感じます。
私は小さいころから動物が大好きで、海外生活という育った環境から興味を持った動物のこと。
現在、第一線で研究できていることに喜びを感じますし、必ずこの成果を現状を変えるパワーに変えていければ、と考えております。
今回、インタビューのご依頼をきっかけにアニマル・ドネーションを拝見し、日本でもやっとこのようサイトができた、と感銘を受けました。
一般の方の後押しもあれば、日本の動物福祉の向上がよりいい方向で進みやすいと思います」
 |
|
 |
|
 |
|