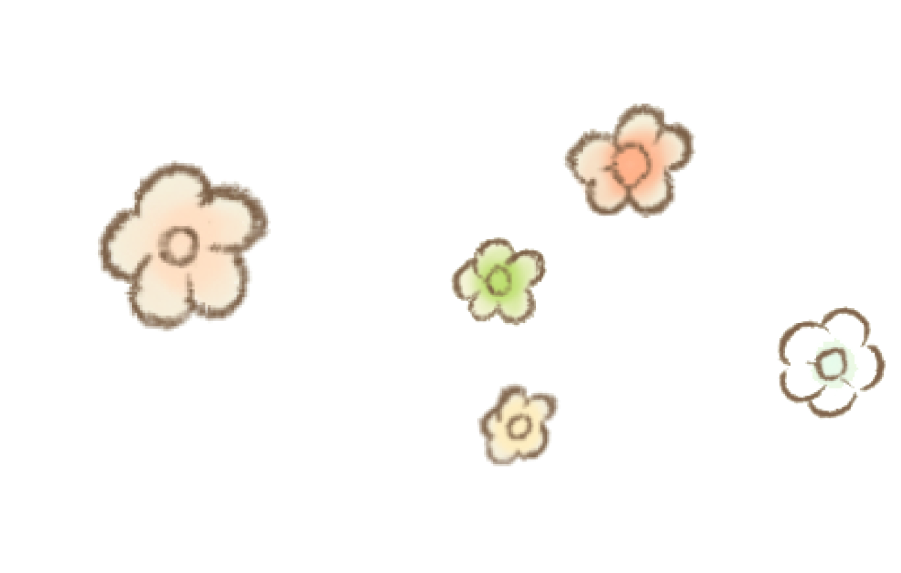活動レポート
活動レポート
動物愛護センター最前線 第2回「現場はどう変わった?取材レポート」
2021.11.23

みなさんは「動物愛護センター」と聞いて、どんなことを思い浮かべるでしょうか?
飼えなくなった動物や野良犬・猫を引き取って次々と殺処分する施設と思っている人もいるかもしれません。たしかに動物愛護の意識が今ほど高くなかった一昔前にはこうした側面があったのも事実ですが、動物愛護センターの多くは現在、殺処分ゼロに向けて動物の命を助けることを一番に考えながらさまざまな取り組みを行い変化を遂げています。
第2回目となる今回は現場レポートをお届けします。
第1回の記事はこちら▷▷
動物愛護センター最前線 第1回「意外と知らない? 動物愛護センターの役割とは」
■名古屋市動物愛護センター
―親しみやすい雰囲気で市民に開かれた譲渡の場にリニューアル―
名古屋の中心部から約1時間ほどのところにある名古屋市動物愛護センター。まだ今ほど動物愛護が叫ばれていなかった昭和60年、動物愛護と適正飼育の普及を目的とした施設「愛護館」を有する画期的なセンターとして設立されました。


譲渡と動物愛護啓発目的の「愛護館」
譲渡の場として機能している「愛護館」は、「市民に開かれた施設にしたい」という職員の声を反映させて平成26年に大幅にリニューアルされました。足を踏み入れると、やさしいピンクや黄色といったカラフルな室内で暮らす猫たちが迎え入れてくれます。「殺風景な施設に不幸な犬猫が所狭しと収容されているのではないか」と思われがちな動物愛護センターのイメージを、いい意味で裏切るアットホームな雰囲気です。

「昔は動物愛護センターというと動物が殺されてしまうところだから行きたくないというイメージが市民の方にもあったのですが、保護猫に興味がある人が増えているのと、この近くにバーベキューやお花見ができる大きな公園があるので、今ではふらっと来てくれます。土日は100人もの方が訪れるのですよ」
そう話すのは、この日案内をしてくれた愛護企画係長の新美さん。取材日は平日だったものの、猫の譲渡希望者が数名来館されていました。

猫飼育室では、譲渡可能な猫たちが新たな飼い主を待ちながら暮らしています。譲渡希望の来館者に向けてそれぞれの猫の詳しいプロフィールが貼られているのが印象的。職員の方が1頭1頭の個性や性格を把握しているからこそできることといえるでしょう。

愛護館には犬の飼育室もあります。犬たちはシャンプーやトリミングだけではなく、毎日の散歩も欠かさないのだとか。さまざまな事情でここに来たということに違いはありませんが、職員の方々にとても大事にされていることが伝わってきます。

愛護館のロビーには、来館者の目に留まるよう適正飼育や動物愛護の理解を深める資料がたくさん展示されています。動物愛護センターの役割や動物愛護への関心が高まるきっかけになっています。
令和2年3月に管理棟の殺処分機を撤去

普段一般公開されていない管理棟には、収容された犬猫を検査する検査室や手術室、飼育室があります。令和元年度には管理棟の改修工事が行われ、殺処分機を撤廃して犬猫の収容スペースを拡張するといった大きな動きがありました。名古屋市は平成21年度には猫の殺処分数が政令都市の中でワースト1位でしたが、現在は殺処分を前提とするのではなく、犬猫の命を救う政策に舵を切っています。適正飼育の啓発や譲渡の促進に力を入れた結果、犬に関しては平成28年度から殺処分ゼロ(譲渡適性問わず)を達成・維持しています。
譲渡ボランティア(団体・個人)との協働
令和元年度の個人への譲渡数は猫198頭、犬10頭でボランティアへの譲渡数は、猫763頭、犬56頭であり、犬猫の命を救うために譲渡ボランティアは欠かせない存在です。現在名古屋市では68の譲渡ボランティアと連携し、それぞれの強みを生かして譲渡を行っています。動物の命に関わることなので団体からの信頼は重要。公平で平等な情報公開を意識して密にやりとりをしているとのことでした。
収容数が減ったことで職員の気持ちにも余裕が
こうして個人や譲渡ボランティアへの譲渡を積極的に行うことで、犬と譲渡適性のある猫に限っては殺処分はゼロになりました。それとともに職員の負担も減るという良い効果も生まれたそうです。センターの過去を知る職員の方に話を伺うと、次のような言葉が返ってきました。
「昔は本当に数が多かった。次から次へと犬猫が収容され、その対応で精一杯で大変でした。生まれたばかりの子猫の引き取りが多すぎて殺処分をせざるを得ない時代もありました。1頭1頭しっかり目をかけて世話ができるようになったので、犬猫にとっても職員にとってもよい環境になってきていると思います。」


「人とペットの共生するまち・なごや」をスローガンに、令和11年度までにすべての犬猫の殺処分ゼロを目指している名古屋市。動物愛護センターが市民に親しまれる施設になったことで、市民に動物愛護や動物福祉について知ってもらう機会が増えたのではないでしょうか。施設の大幅なリニューアルはすぐにできることではありませんが、今後各地にこうしたセンターが増えていくことを期待します。
【施設情報】
名古屋市動物愛護センター
住所:〒464-0022 名古屋市千種区平和公園二丁目106番地
電話:052-762-1515(愛護館)
開館時間:10:00~12:00、13:00~16:00
休館日:月曜(月曜が祝日の場合は直後の平日)
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-7-2-0-0-0-0-0-0-0.html
■茨城県動物指導センター
―ワースト1位からの脱却―
茨城県の収容数が多い理由
次に向かったのは、茨城県笠間市にある茨城県動物指導センター。茨城県はかつて犬の殺処分数の全国ワースト1位が続いており、一部ではセンターへの批判の声が上がっていました。しかし、令和2年度は10年前と比較すると犬の殺処分数約99%減少、猫88%減少と大幅に改善。その背景にはどのような取り組みや努力があったのでしょうか。センターで愛護促進を担当している吉田さんにお話を伺いました。

「茨城県は野犬の捕獲が多いのが特徴です。敷地の広い戸建ての住居が多く、温暖な気候であることから、犬が育ちやすい環境なのです。また、犬を家の外で飼っている飼い主がいまだに多く、逃げたりなどして屋外で繁殖した結果、野犬になりセンターに収容されます」
たしかに、気候や環境によって繁殖数や捕獲数が変わることを考えると、都道府県の収容数の多い少ないは一律に比較できないといえるかもしれません。茨城のように犬猫が“育ちやすい”県の収容数が多くなってしまうのは、ある意味仕方がないともいえます。平成30年度の犬の収容数は1426頭で全国ではワースト9位。同年猫は1515頭で、こちらは全国で21番目に多い数です。ワースト1位を脱却したとはいえ、まだまだ多いのが現状です。
増える犬をどう守っていくか
犬猫が暮らす動物棟を見学すると、成犬の多さに驚かされます。年間で収容される数だけでいうと猫のほうが多いのですが、犬は人間に慣れていなかったり、脱走の可能性があったりするため、ボランティア団体や個人への譲渡に慎重にならざるを得ず、収容期間が長くなってしまうのです。

衛生管理が徹底していた。

特に野犬だったと思われる気性の激しい中型~大型犬が目立ちます。犬舎は個室、ケージ、大部屋の3タイプが複数ありました。ケージは決して大きいとはいえないものの、性格や性別を考慮して振り分けているとのこと。空いているケージもちらほらあったり、どの大部屋もすし詰めではないことから、パンク状態ではなさそうです。大部屋ではちょうど職員の方がおやつをあげているところで、愛情を込めて接している様子がうかがえました。

ちなみに上の写真の場所には以前、殺処分直前の犬が収容されていました。かつて殺処分数ワースト1位だった茨城県が殺処分機の稼働を止めたのは、センターの意義が犬猫の処理から愛護へと変化した象徴といえるでしょう。
一方、人間に慣れていない野犬は譲渡適性が低いとみなされ、今でも殺処分の対象になる可能性が高くなります。しかし、このセンターでは令和2年からドッグトレーナーによる犬のトレーニングを取り入れ、譲渡されやすくなるよう訓練をしています。令和元年にはセンターの敷地内にある古墳にドッグランを新設。犬のストレス解消や健康維持に効果が期待できます。こうしたことも大きな変化といえるに違いありません。

動物の管理から動物の愛護にシフト
茨城県では、平成28年12月に「茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例」が、そして平成29年度に「犬猫殺処分ゼロを目指すプロジェクト事業」が始動しました。それ以前からの地道な活動もあり、平成2年度の犬猫殺処分頭数が2万7512頭だったのに対し、令和元年には150頭まで減少(収容中の死亡を除く)、譲渡数は同年223頭から2124頭に増えるという実績を上げました。
「まず、入口対策として収容数を減らすために、動物愛護の啓発を積極的に行うようになりました。飼い主のいる犬猫に関しては室内飼育を徹底させ、不妊・去勢手術の必要性を訴えています。年配の方を中心に、放し飼いでも問題ないと思っている方はいまだに多いのですが、直接出向いて根気強く説明して犬を繋いでもらうようにしています。また、小学校に向けて、動物ふれあい授業を行い動物の命の大切さを教えています。

出口対策となる譲渡は、平成14 年からボランティア団体さんのお世話になっています。当センターでは、模範的な飼い主さんを育成することを目的として、一定の条件をクリアした方に成犬の譲渡を行っていますが、それ以外はすべてボランティアさんに引き取っていただいているのです。センターが収容された犬猫でパンクしないのは、約80の登録ボランティアの方々のおかげです」
譲渡の促進とボランティアさんの負担を軽減するために、成犬・成猫の譲渡の際はセンターで不妊去勢手術を実施したり、動物病院で手術を行えるチケットを交付しています。
なんとかしなければという思いで動いてきた結果
収容数はまだ多いという現実はあるものの、過去と比べると数字も犬猫の環境も徐々に改善している茨城県。
「10年ほど前は、捕獲の依頼や苦情の電話が鳴りやまず、職員たちも疲弊していました。しかも毎日毎日犬猫が収容されるので個別管理ができず、犬種や性格問わず曜日ごとに振り分けた部屋に入れていました。その頃から比べると今は改善された点がたくさんあります。収容頭数が減ったことで犬猫へのワクチンの接種や血液検査も行えるようになり、感染症の蔓延も防げています。生まれたばかりの子猫のミルクやりを行うことなんて、今より収容頭数が多かった当時はとてもじゃないけれどできませんでした。

『動物の命を救いたい、殺処分をゼロにしたい』という気持ちをボランティア団体さんと共有しながら、なんとかしなければという思いで動いてきた結果が少しずつ出てきています。これからも終生飼育や不妊去勢手術の徹底などの啓発活動や譲渡活動に力を入れていきたいです」
「ワースト1位」というイメージが一度つくと、挽回するのが難しいのだとか。職員の方の努力や気持ちがなかなか伝わらないこともあると言いますが、諦めずに歩みを進めていく姿が印象的でした。
【施設情報】
茨城県動物指導センター
住所:〒309-1606 茨城県笠間市日沢47
電話: 0296-72-1200 (平日8:30~17:15)
https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/hokenfukushi/doshise/index.html
第3回に続く▷▷
 このテーマのゴール
このテーマのゴール


ゴール 8
殺処分をゼロに
殺処分される犬猫は年間約9,000頭(令和5年 度環境省 動物愛護室)。16万頭以上だった10年前と比べると激減しています。しかし譲渡向上は改善の余地があり、ゼロを目指すべきです。あらゆる角度から譲渡向上を考えます。