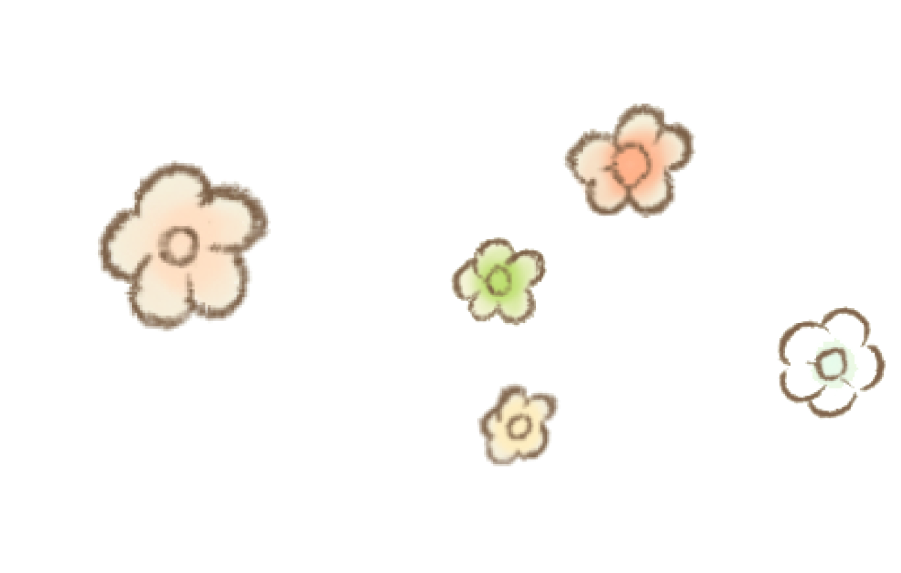活動レポート
活動レポート
愛するペットとの別れと向き合い、未来へ一歩踏み出すためにできること ーグリーフケアの大切さー
2025.05.08

ペットをお迎えするからには必ず覚悟しなければいけないのが看取り・死別です。ペットロスという言葉もよく耳にするのではないでしょうか。
迎えるであろう愛する犬猫との別れに対して、飼い始めた時からできることから看取った後の心の対応まで、動物医療グリーフケアが専門の阿部美奈子先生にお話しをお伺いしました。
犬の平均寿命は14.90歳、猫の平均寿命は15.92歳と言われています。[1]いずれにせよ人間の一生よりも短いことがほとんどです。一度お迎えしたからには、その犬や猫が一生を幸せに全うできるために、飼い主としてできることを実践しましょう。
グリーフと向き合うための基礎知識
そもそもグリーフとは
グリーフ(grief)という言葉は、愛する人や大切な存在を失った際に生じる深い悲しみや嘆き、苦悩のことを指します。これは、死別や離別だけでなく、離婚、病気、引っ越し、失職など、さまざまな喪失体験によっても引き起こされます。そして、誰にでも起こりうる自然な反応であり、病気ではありません。
グリーフの感じ方は人それぞれです。
感情的な反応:深い悲しみ、涙が止まらない、感情の麻痺、不安、孤独感、罪悪感など
身体的な反応:睡眠障害、食欲不振、疲労感、頭痛、肩こり、動悸など
それだけでなく、今までの日常の行動が変化して、ぼんやりしたり、涙が溢れてきたり、引きこもったりということもあります。
グリーフは人間だけが感じるもの?
グリーフとは、人間だけが持つ感情なのでしょうか。
2016年に英国王立協会誌 Biology Letters に発表された論文「Dogs recognize dog and human emotions」[2]で、犬が人間と他の犬の感情を識別し、それに対応する心の中のイメージを持つ可能性があることが発表されました。
この論文の結論として、犬は視覚(表情)と聴覚(声のトーン)を元に組み合わせて感情を判断し、単に特定の表情や声に反応するだけでなく、ポジティブ・ネガティブな感情の概念を持ち、それを基に状況を判断することができるということです。
程度の差はあるかもしれませんが、猫も近い感覚を持っていると推定できます。このことから、「人間がグリーフを感じている際に、それを読み取った犬や猫もグリーフを感じること」が予想されます。
阿部先生は、犬猫の感情認識について人間で言うと1~2歳と捉え、彼らが感じるグリーフを人間が想像することで、ケアをする際の配慮の幅が広がると提唱されています。
例えば、ブリーダーのところで母犬と兄弟と過ごしていた子犬が、人間にお迎えされる時。犬の視点に立つと親兄弟と離れる時と捉えられ、子犬が感じる初めてのグリーフということになります。人間と全く同じと言えるかどうかは別としても事情を知らない幼い犬や猫が母親や仲間、環境との分離によってグリーフが生まれると阿部先生は考えられました。
このように考えると、ペットへのグリーフケアが大切なことを理解できるのではないでしょうか。
次の章からはいくつかのシーンに分けて、最愛のわが子を迎えてから看取るまでにできることをお伝えします。
出会いから別れ、そしてその先の未来へ
誰しもが明るい未来を想像して犬や猫をお迎えしますよね。出会いの時期から別れのことを考えないといけないの?と思われるかもしれません。
この記事で紹介するのは、その子の犬生や猫生を最高のものにすることが、最高の飼い主のグリーフケアになるという考え方です。
一度お迎えしたら、飼い主は犬や猫を幸せにすることが使命です。きっとそれ以上に、幸せを返してくれるのが犬や猫という存在だと感じることでしょう。
出会いから健常期
まずは飼い始めた時から、この子はどんなところで安心するのか、どんなことが苦手なのかを、よく理解してあげることが大切です。わが子に寄り添って、共感してあげてください。事象に対する感じ方が人それぞれなのと同様に、犬や猫もそれぞれの特性によって違います。
最も大切なことは、わが子に間違いなく安心できる「テリトリー」を与えることです。
そのテリトリーでは、安心して眠れる、いつもフードが提供される、きれいな水がある、飼い主の笑顔が見られるなどたくさんの要因があります。あくまでも犬や猫が主役で、その子の視点で見た時に安心・安全かどうかを考えてあげてくださいね。
お迎えした時から、なんでも相談できるかかりつけの獣医を探すことも重要です。犬や猫はワクチンや健康診断などで、動物病院に行くことも多々あります。人間と同じで、もちろん相性もあります。連れて行った時に、犬や猫の気持ちに寄り添ってくれるかがひとつの判断基準になります。
「この動物病院の獣医さん、看護師さんならわが子を任せて大丈夫!」と、飼い主が思える動物病院を探しておきましょう。
治る病気にかかった時
人間と同じで、犬や猫も体調を崩すことがあります。
その時に大切なのは、飼い主が悲しい顔、心配な表情や行動を見せないことです。
もちろん、心配な気持ちはよくわかります。ただ、その心配な表情がいつもの飼い主ではないと感じてしまうことから、わが子は余計不安になってしまいます。それが自宅でも続いたら、テリトリーが脅かされていると感じてしまいます。
心配な時には、かかりつけの獣医やペットを飼っている仲間に不安を伝えて、飼い主自身の心を落ち着けるようにしましょう。気持ちを誰かに伝えたら、わが子にはいつも通りの顔で、いつも通りのテリトリーを守ってあげましょう。
また、治療の過程で、どんな投薬の方法がいいのか、どんな体勢なら安心して休めるのか、ぐっすり眠れる毛布はどれかなど、しっかりとわが子の特性を観察しながら、ベストな治療方法、対応方法を探してあげることが大切です。

こうして観察しておくことで、治らない病気が発覚した時に、何をしてあげるのがベストかをシュミレーションできます。
治らない病気が発覚した時
人間同様、犬や猫にも寿命があります。わが子の寿命を宣告された時、あなたはどう思われるでしょうか。きてほしくない別れの時を想像し、ものすごく不安に苛まれたりするかもしれません。これを予期グリーフといいます。
例えば、かかりつけの獣医から「この子の身体で癌が進行しています」と言われたら、「癌はどうやって治るのか?抗がん剤?放射線?どうしたらいいの?」と癌について、頭がいっぱいになってしまうかもしれません。その時点で、あなたは、その子を見ているのではなく、その子の中にある癌を見ていることになります。その状態で、いつも通りに接してあげるのは難しいでしょう。
一方で、わが子の立場にたって考えてみましょう。動物病院に連れて行かれたと思ったら、いきなり飼い主が暗い顔になってしまい、元気がない。家に帰ってもため息ばかりついている。飼い主の予期グリーフを受けて、当然不安になってしまいます。
犬や猫は体調が悪かったとしても、病名が理解できるわけではありません。ここでも大切にしてあげたいのは、安心安全のテリトリーです。飼い主さんの温かい笑顔、治る病気だった時に見つけておいた、楽な投薬方法など、なるべく普段に近づける努力をしてあげましょう。入院が必要な場合でも、お気に入りの毛布を持ち込んだり、お見舞いに行ったりとできることはあるはずです。
看取りの時まで、なるべく日常に近づけてあげることが、その子のテリトリー、そして尊厳を守ることになるのです。
看取りの時、その後
どんなに穏やかに看取っても、大変な介護を経て看取っても、飼い主はグリーフに直面し、ペットロスになります。それは、その子が与えてくれた愛や影響の大きさを考えると当然です。悲しみや涙を我慢する必要はありません。
いつも一緒にいてくれた、まっすぐな目で見つめてくれた、甘えてくれた、たくさん与えてもらっていたことに改めて気付かされます。ここでは、自分がどのようにグリーフの傷を癒していくか、時期に分けてご紹介します。[3]自分がどのような状態かを把握することで、少し客観的に見られるようにしておきましょう。
衝撃期
ショックで頭が真っ白になって、考えることができず、心がこれ以上の傷にならないように自己防衛している状態です。緊張や焦りもみられます。
悲痛期
少し現実味が増してきて、不安や心配、恐怖、喪失した原因を探して、後悔、自責や他責、罪悪感などでマイナス思考に引っ張られ、心が痛む時期。もしかしたらもう一度会えるかもしれない…と心が亡くなったわが子を取り戻そうとすることも。また、この時、睡眠障害や食欲不振、疲労が見られる場合もあります。
回復期
現実を受け入れ、喪失したことを認める時期です。出会えた幸運に感謝が生まれ、できなかったこともあるけれど、できたこともあったと評価できるようになります。これからどうしたらいいかをプラス思考で肯定的に考えることができるようになって勇気も出てきます。
再生期
回復をもう一歩前進させる時期です。新しい未来を考えて歩き出すことができ、グリーフという喪失でできた心の傷が、自分のペースで悲痛期や回復期、回復期から再生期を行ったり来たりしながら再生へと向かっていきます。きっとこの時期には、最愛のわが子がしっかりと心に宿り、前に進むことができるようになるはずです。
阿部先生からのメッセージ

ほとんどの人は最愛のわが子を亡くした後に、とてつもなく衝撃を受けます。カウンセリングなど外部の力を借りることも、ペットロスのダメージを減らす手助けになるでしょう。現代の日本では、核家族化が進み、愛犬・愛猫の存在はますます大きくなっているので、より悲しみが深くなっているようにも感じます。
一方で、元気な頃からずっとその子の気持ちに共感して、テリトリーを守りながら、楽しい時間を共有したり、自分が落ち込んだ時にその子から癒しとパワーをもらったり、これ以上ないほど愛を注いだと感じられたとしたら、最期の看取りの時に悲しさはありながらも、感謝の気持ちで見送ることができるのではないでしょうか。そして、わが子はあなたの心の中で生き続けるはずです。
愛犬・愛猫にとってあなたは唯一無二で、大好きな存在です。
犬生・猫生を全うできるように、寄り添ってあげてくださいね。
阿部美奈子先生プロフィール
マレーシア在住 獣医師 動物医療グリーフケアアドバイザー
ペットと人の心を元気にする獣医師。「ペットと人のハッピーライフを出会いから死後まで」を合言葉に「待合室診療」というこれまでにない診療スタイルで、自らが考案した動物医療グリーフケアを展開している。動物医療グリーフケアはペットや飼い主だけではなく、命に向き合う医療者にとって重要な視点となる。マレーシアと日本を毎月行き来しながら、動物医療グリーフケアを幅広く実践、「ペット主役」のオンリーワン医療を目指す。ペットロスカウンセリングを行うと同時に「ペットが生きている間に取り入れるグリーフケア」の大切さを提唱。その他にも、カウンセリング、人材育成セミナーや講演活動、執筆にも力を注ぐ。著書の「犬と私の交換日記」「猫と私の交換日記」にはペットと人の心の絆を守るグリーフケアのエッセンスが詰まっている。
2019年5月 ペットライフのトータルコンサルタント会社「合同会社Always」設立
2020年8月 動物医療グリーフケアの商標登録完了
[1] 一般社団法人ペットフード協会 令和6年(2024年)全国犬猫飼育実態調査
https://petfood.or.jp/data-chart/
[2] “Dogs recognize dog and human emotions”
Natalia Albuquerque, Kun Guo, Anna Wilkinson, Carine Savalli, Milena Otta, Daniel Mills
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2015.0883
[3] 二見書房 犬と私の交換日記
 このテーマのゴール
このテーマのゴール


ゴール 11
健やかな一生を
目の前にいる可愛い子犬・子猫が、どこで、どのように生まれたのか、思いを馳せてみましょう。親元から離され、長距離輸送により精神疾患を病んだり、遺伝子疾患などの健康問題を抱えた子が存在しています。多くの犬猫が健康体で人生のスタートを切れるようにするための方法を考えていきます。