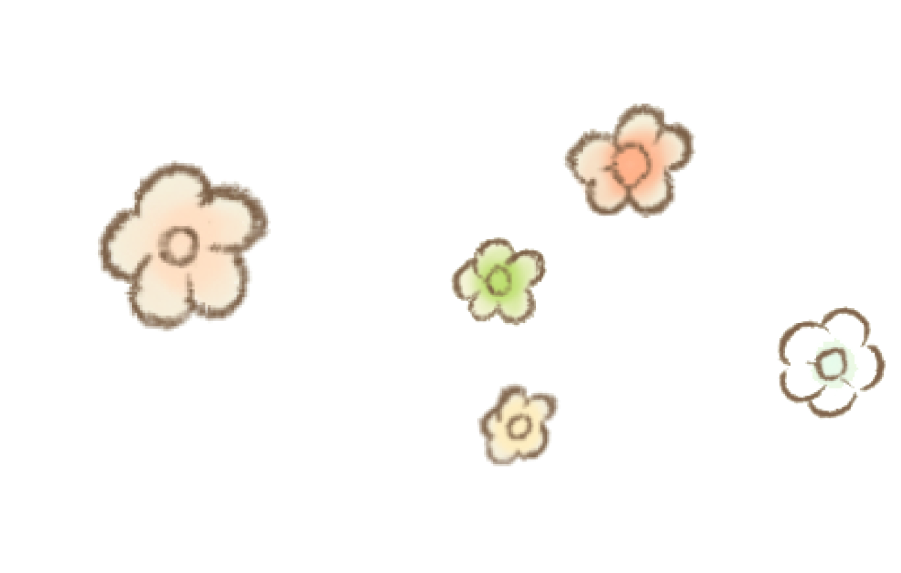活動レポート
活動レポート
Part1 ペット(伴侶動物)との新生活。家族として必ず知っておきたいこと。
2025.06.21

新しい家族として犬や猫を迎えることは、私たちにとっても新たな生活の始まりです。伴侶動物が健康で、できるだけ長く一緒に過ごせるようにするために、事前にどのようなポイントを押さえておくとよいでしょうか。赤坂動物病院の柴内晶子獣医師からお話を伺いました。
ライフステージに合わせた暮らしを
犬や猫と共に暮らしを始める上で大切なのは、人間のライフスタイルと伴侶動物のライフステージを合わせた暮らしをすることです。犬や猫は約1年で成犬・成猫に成長し、その後、人間の4倍の速さで年をとります。犬や猫のライフステージごとに起こりうる出来事を把握し、家族として心構えを持っておきましょう。
ライフステージは大きく、子犬・子猫期、成犬・成猫期、高齢期に分けられます。家族として犬や猫を迎える前に、各ステージに必要な食事、グルーミングなどの日常ケア、コミュニケーション・社会性などを知っておくことが大切です。
また、お迎えの前に家族である皆様のライフスタイルが、犬と猫のどちらとの生活がより合っているか?などについて、獣医師やインストラクターなどの専門家と「暮らす前カウンセリング」の機会を持つことも大切です。暮らしはじめて「こんなはずではなかった。」ということがないようにしましょう。
お迎えの前から、かかりつけ医を決めて、定期的な健康診断を受けることが望ましいです。病気の発見のためだけではなく、正常時の状態を把握しておくことで、参考にできるデータが蓄積し、結果として病気の早期発見につながります。健康診断を通して、病院に何でも相談できる関係性を築いておくと心強いですね。健康診断は、5歳までは年1回、5歳以降は年2回から4回が目安です。
7歳頃からは悪性腫瘍の発生しやすい年齢になりますので、特に目を光らせておきたいですね。腫瘍は身体の表面や見えるところだけに発生するわけではありません。専門的な画像診断で見つかるケースもあります。腫瘍が2週間くらいの非常に早いスピードで進行する場合も、稀ではありますが、あり得ます。検査のみならず、いつもと何かが違う、という家族の感覚が、意外に大切なセンサーになります。
身体的・性格的個性を理解する
ライフステージについて大枠を知った上で、お迎えする犬や猫の個性を理解しましょう。犬種や猫種の違いだけではなく、それぞれが身体的な個性を持っています。
一例ですが、太りやすい、目やにが出やすい、などというような違いがあります。ブラッシング、耳、口、爪などの毎日のお手入れやBCS※のチェックを通して、愛犬・愛猫とコミュニケーションを図り、日々の健康な状態を把握しましょう。
※BCS(ボディ コンディショニング スコア)は、見た目と触れた状態から、体型(特に脂肪の付き具合)を9または5段階で評価したスコアを指します。痩せ(BCS 1)から肥満(BSC 9または5)で判断します。
また、一般的な表情やボディサインを学び理解することも大切です。例えば、犬がしっぽを振っているときは喜んでいる場合もありますが、興奮している事もあります。猫は、ゴロゴロと喉を鳴らすときはリラックスしていることが多いです。耳を後ろに引いているときは警戒していたり、緊張している場合もあります。目つきや行動なども、共に暮らす中で理解を深めて行きましょう。
犬や猫の性格にも個性があります。個性を理解することで、信頼関係が深まり、お互いの安心につながります。また、見逃しやすい小さな異変にも気がつきやすくなるでしょう。そして、わからないことがあれば、いつでも専門家に相談できるようにしておくと心強いですね。
社会性の進め方を考える
最後に、人と暮らす伴侶動物として、社会性をどう身につけていくか考えましょう。犬や猫にとっての社会性というのは、他の生き物との関わりだけではありません。新しい家の窓から見える景色、家族が関わる様々な人々、動物病院のスタッフや生活音なども含めた周りの環境に触れること全てを意味します。犬と猫は伴侶動物の代表選手です。人間社会の中で、人も動物もストレスなく暮らす上で、社会化は大変重要なポイントです。
新たに迎えた愛犬・愛猫は、すぐに環境に慣れさせていける状態なのか、または、まだその状態ではないのかを含め、個性に合わせた社会化のプログラムを考えます。書籍その他から、幅広く情報を把握しておくことも大切ですし、インストラクターや主治医、動物行動学を学んでいる獣医師などのアドバイスを受けることもお勧めします。多くの情報から、愛犬・愛猫にとって適切な方法を見極めましょう。多くの場合はしつけカウンセリングなどを受け、家での伴侶動物の様子を含めて、できれば家族全員で理解をしておくと、その後の暮らしの助けになります。
お迎えする前の愛犬・愛猫の生活環境を踏まえ、ライフステージを考慮しながら、社会化を一気に進めるのではなく、少しずつサポートをすることがポイントです。
次回Part2では、ライフステージに合わせた伴侶動物との暮らしのポイントについて詳しく触れていきたます。
インタビュイー
赤坂動物病院 柴内 晶子先生

私は生まれた時からすでに環境の中に伴侶動物との暮らしがありました。時代は変わっても人が優しい気持ち、地球は人類だけのものではないこと、自然との関わりを忘れないために、自然界から贈られたギフトではないかと感じる時があります。高齢の愛犬が安心して熟睡している寝顔を見るとき、地下駐車場を独り走っていた子猫だった愛猫が暖かいクッションで伸びをしながら私を見る時、そのまなざしに数万年の時を共に駆け抜けてきたかけがえのない「奇跡のパートナー」との「絆」を感じます。日々の動物病院の現場の中で患者さんとして接する動物達とそのご家族も同じような心の絆「人と動物の絆」をもっていらっしゃると思います。「うちの子だったら」という視点でご家族と動物達に接していくように心がけています。「伴侶動物は人類の宝物」ですね。
2015年8月~赤坂動物病院院長に就任 役職:厚生労働省薬事審議会委員、元農林水産省獣医事審議会委員、公社)日本獣医師会会員、公社)日本動物病院協会会員 内科認定医、(社)人と動物のきずな福祉協会理事、特定非営利活動法人ちよだニャンとなる会顧問、(社)日本動物愛護協会評議委員 他
著書:「THE DOGシリーズ」「犬のきもちがわかる本」「子犬がわが家にやってくる」「勤務獣医師のための臨床テクニック」「イラストでみる猫の病気」 他
 このテーマのゴール
このテーマのゴール


ゴール 11
健やかな一生を
目の前にいる可愛い子犬・子猫が、どこで、どのように生まれたのか、思いを馳せてみましょう。親元から離され、長距離輸送により精神疾患を病んだり、遺伝子疾患などの健康問題を抱えた子が存在しています。多くの犬猫が健康体で人生のスタートを切れるようにするための方法を考えていきます。