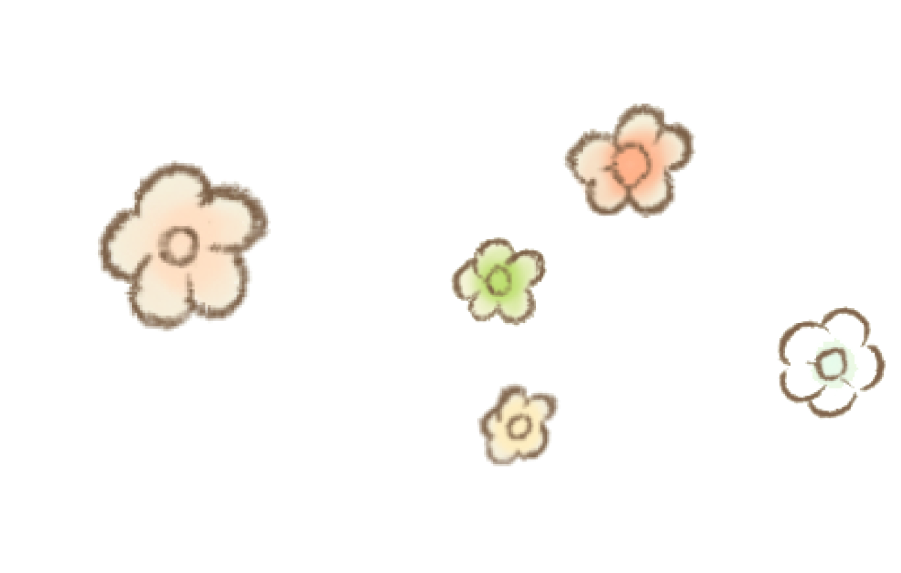活動レポート
活動レポート
犬猫保護団体の「現場」と「動物福祉」を可視化する ~犬猫保護団体 活動白書2025を読み解く~
2025.09.02

1. はじめに:保護活動の「いま」を知る意味
保護された犬や猫と暮らす人が身近に増え、保護犬や保護猫という言葉も定着してきたように思います。けれども、その保護活動を行なっている団体がどのように考えているのか、どのように保護動物の福祉を考えて世話をしているのか、どのような課題を抱えているのかを深く理解している人はまだ少ないかもしれません。
「犬猫保護団体 活動白書2025」は、全国176の団体から寄せられた声をもとに、保護活動の実態や保護団体の考えを可視化した先駆的な調査です。この記事ではこの白書を、AWGsのゴールを踏まえて動物福祉という視点から読み解きながら、動物保護団体による命を守る営みのリアルを一緒に考えてみたいと思います。
2. 動物福祉って?
ところで「動物福祉」という言葉を聞いて、どんなイメージが浮かぶでしょうか。病気やけがを治してあげること?きれいな場所で飼うこと?それとも、愛情をかけて世話をすること?
そもそも「福祉(Welfare)」とは、広辞苑によれば「幸福」や「生活の安定・充足」を意味します。動物にとっての福祉も同様に、「身体的・精神的に健康で、幸福であり、環境と調和していること1)」が重要なポイントになります。
実は国際的には、1965年にイギリスで提唱された「5つの自由(Five Freedoms)」が、動物福祉の基本的な考え方として知られています。これは動物が本来持つべき最低限の権利ともいえるもので、以下の5つが大きな柱になります。
- 飢えや渇きからの自由
- 肉体的苦痛や不快からの自由
- 傷病からの自由
- 恐怖や不安からの自由
- 本来の行動を表現する自由
この「5つの自由」は、世界中の動物保護・福祉政策の基盤となっており、日本国内でも少しずつこの視点が広がってきています。
つまり動物福祉とは、単に「生かすこと」ではなく、「どう生きているか」にまで目を向ける考え方なのです。保護された犬や猫たちに対しても、この考え方の下で幸せに生きられる環境を整えていく必要があります。
3. 保護団体の活動
動物保護団体というと、「捨てられた犬や猫を引き取って世話をする団体」といった漠然としたイメージを持っている方も多いかもしれません。けれども、実際の活動はそれだけにとどまりません。
団体の多くは、保護された動物たちに医療ケアを施し、社会性を身につけさせ、人に慣れさせるトレーニングや栄養管理、適切な環境づくり、譲渡への試みまでを一貫して行っています。これは、単に「保護する」ための活動ではなく、「動物達の福祉を守る」ための努力でもあります。一頭一頭の背景や性格に応じてケアの内容を変えたり、譲渡先の家庭環境を慎重に確認したりするなど、非常にきめ細かい対応を行なっている保護団体もあります。
また保護活動と並行して、捨て犬・捨て猫を減らすための啓発活動や多頭飼育崩壊の防止策にも取り組んでいたり、地域イベントを活用して譲渡会の開催や寄付の呼びかけなど地域との接点も積極的に広げているところもあります。
こうした日々の活動の中で、限られた人員と資金の中でも保護団体が犬や猫の福祉をできる限り高めようとしていることが、「犬猫保護団体 活動白書2025」からも見えてきます。これから少し白書を深掘りしていきましょう。
4. 活動白書から見えてくる保護団体の現状や意識
保護活動の現場はどのように成り立っているのでしょうか?活動白書では、全国176団体からの回答をもとに、運営体制や保護の流れ、資金状況などの実態が定量的な数値と共に明らかにされています。この4章ではその中でも特に、保護団体の基盤に関わる3つの要素に注目してみたいと思います。
(ア) スタッフ体制と活動規模
日本においてスタッフ体制やどれくらいの大きさの保護団体が多いのでしょうか?白書に記載されているデータを一緒にみていきましょう。
まず目につくのは、スタッフの約76%が無償のボランティアとして活動しているという点です。中には有償で取り組む職員を抱える団体もあるものの、日々の運営が善意の時間に支えられている構造が浮かび上がります。
団体の規模としては30頭未満の団体が約44%(小規模)、100頭未満が約39%(中規模)となっており、調査に協力していただいた団体の多くが中小規模であることがわかります。同様に、猫のみを保護している団体が約56%で中央値で29頭ほど保護、犬猫の両方を保護している団体が約33%で中央値で44頭ほど保護していることがわかりました。
つまり、調査に協力いただいた団体が日本全体を表している仮定をとれば、日本には中小規模の団体が多く存在し、そこにいる保護動物達は無償のボランティアによって管理・ケアされているケースが多いということが考えられますね。
(イ) 保護経路と保護団体の意識
保護団体が保護している犬猫の多くがどこから来ているのかご存知でしょうか?ここでは保護団体がどのような場所から動物たちを保護しているのか現実のデータを一緒に見ていきましょう。
実は犬や猫の保護経路は、犬が行政機関(動物愛護センター等)からの引き取りで74%、猫は野良や捨て猫、迷子猫の保護が64~76%と主流となっています。犬と猫で傾向が大きく異なることが見えてきます。
これは保護する動物の種類によって行政と民間団体が役割を分担しながら連携することの必要性が高まっていることを物語っています。
では、このようにさまざま場所から動物たちを保護している団体は動物の福祉についてどのような課題を持っているのでしょうか?以下がそのデータになります。
調査に協力していただいた約80%の団体が動物たちの福祉に関して課題に感じていることとして、一般飼育者の飼育放棄や多頭飼育崩壊に関する点を挙げていました。これはあまり深く考えずに「感情を持つ生命存在」を購入したり飼育してしまう現代を生きるオーナーに対して課題感をもつ団体が多いことを示しているのかもしれませんね。
(ウ) 資金の透明性と課題
この章の最後に団体運営においてよく課題に挙げられる資金についてどのように考えている団体が多いのかデータを見ていきましょう。
アンケートの結果からも保護活動の課題として資金面を挙げた団体は約60%となっていることがわかりました。よく言われるように、これは多くの団体が保護活動の資金を寄付金や譲渡費用に依存しており、常に綱渡りのような運営を強いられていることが推察されます。
資金の透明性に関してのアンケート回答を見ると、収支報告を公開している団体の割合も小中規模の団体で約76%、大規模の団体で約90%となっているようです。
つまり保護という大変な活動を行うと同時に多くの団体が信頼を得ながら継続的に活動していくために資金の使途や方針を明確にする努力も行なっていることが推察されます。
5. 動物福祉を重視している犬猫保護団体~AWGsのゴールに関連して~
そして今回の白書でもう一つ注目すべきは、保護団体が「ただ命をつなぐ」だけではなく、動物福祉の視点を持って保護動物の生活の質つまり福祉を高めようとしていることが、さまざまな回答から読み取れる点です。ここでは、団体が実際に行っている福祉的配慮をAWGsのゴールを踏まえて4つの観点から見ていきましょう。
(ア) 散歩やしつけ
まずは動物福祉の基本である5つの自由では「本来の行動を表現する自由」や「肉体的苦痛や不快からの自由」、AWGsではゴール2の「本能的欲求を満たそう」やゴール6の「犬猫の社会性を向上」について考えていくために非常に重要なことである、散歩としつけについて保護団体が行なっていることをデータともにみていきましょう。
毎日30分~1時間または1時間以上の散歩を行なっている団体は約61%で、中小規模の団体のほうが散歩にかけられる頻度や時間が長い傾向がみられました。
さらに、しつけに関しても約95%の団体でなんらかのしつけを行なっていました(トレーナー、担当または群れによるしつけ)。これは保護団体の多くが福祉において重要な動物たちが「本来の行動を表現する」ことを重視する取り組みを心がけており、譲渡後の家庭における適応にもつながる重要な活動をしっかり考慮していることを示唆しています。
多くの団体が、犬に対する定期的な散歩やしつけトレーニングを行っており、ストレスの軽減や社会性の向上を図っていることがみてとれますね。
(イ) 犬猫の栄養管理
食事は生きるためだけでなく健康を維持し、心身の安定にも直結する要素です。そのため動物福祉の柱のすべてに関わってきます。AGWsのゴール11の「健やかな一生を」の達成にも必要不可欠な要素になります。では保護団体はどのように保護動物たちの食事についてケアしているのでしょうか?活動白書のデータを一緒にみていきましょう。
まず良質なフードを与えることを方針としているのが約82%、さらに年齢別、アレルギーや病歴別などそれぞれ個体の栄養ニーズに合わせたフードを与えていることを方針としている団体の割合は約70〜79%となっていますね。
さらに約40%の団体が食事の頻度を考慮したり、おやつの工夫を行っていたり、一部の団体では、手作りで作っているところもあるようです。
このように保護団体の多くがただ食事を与えるのではなく、それぞれの保護動物たちを見て栄養管理を行なっていること、つまり保護動物たちの福祉を考慮して食事を与えていることが示唆されます。
(ウ) 医療ケアの充実
医療ケアは動物福祉において「肉体的苦痛や不快からの自由」「傷病からの自由」「恐怖や不安からの自由」などに関わるもっとも重要な事柄の一つです。先の栄養管理と同様にAGWsのゴール11「健やかな一生を」、それだけでなくゴール5の「すべての犬猫へ人のぬくもりを」やゴール8「殺処分をゼロに」にも大きく関わっています。
しかしながら、ワクチン接種や避妊去勢手術だけでなく、慢性疾患や怪我を抱えた個体への医療対応はコストがかかることから普通にペットを飼育していても難しい対応が強いられることが多くあります。
そんな中で保護団体はどのような対応をしているのでしょうか?傾向をみてみましょう。
約半数の保護団体が保護動物たちへ定期検診を行っているとともに、予防接種を行なっている団体は95%と全国平均の予防接種率約70%2)と比べると25%以上高いことがわかりました。このデータから保護団体の多くが保護動物たちの健康を強く配慮していることが示唆されますね。
(エ) 保護環境の整備
犬猫が過ごす保護環境の整備は「肉体的苦痛や不快からの自由」、「恐怖や不安からの自由」や「本来の行動を表現する自由」、その上でAWGsのゴール1「犬猫に快適な生活の場を」を達成するために非常に重要な事柄のひとつです。
この観点において、保護団体の活動を可視化してみると実に94%もの保護団体が犬猫のストレスや心理的なケアのために清潔な環境を作り出す取り組みを行なっていることがわかりました。さらに適切な室温管理や給餌も90%以上の団体が取り組んでいることがわかりました。
そのうえで大きな施設では小さな施設よりも自由になれるスペースを作ることに配慮している一方で、小さい施設ではスペースが小さくてもリラックスできる空間づくりを考慮している傾向もみられています。
それゆえ、それぞれの施設ではただ保護するのではなく、しっかりと動物福祉に考慮した保護を行なっていることが示唆されます。

6. おわりに:命を支えるために我々ができること
活動白書を通じて見えてきたのは、犬猫の命を守る保護団体の存在が実は私たちの日常のすぐ隣にあるということ。そしてその活動が、単なる「保護」ではなく、感情のある生命存在である犬猫の「身体的・精神的に健康で、幸福であり、環境と調和していること」という福祉の視点に根ざしているという事実です。
もし実際に保護団体から犬猫を引き取る場合には、動物福祉を尊重している団体かどうかという視点を加えていただけたら、保護犬猫を介してその団体ともいい関係を築けることと考えられます。
一方で、それほどまでに丁寧に動物と向き合っている団体が、世間から十分に理解されていない、あるいはまだ活動資源に対して課題を感じている現実も浮かび上がってきました。人間の生活と同じように動物の暮らしにも「質」があります。食べられるか、眠れるか、痛みはないか、不安はないか。そしてそれを支える活動が、目立たないところで静かに続いていることを少しでも多くの人に知ってもらいたいと思っています。
この記事をここまで読んでくださった方には、ぜひ一つ、何かできることを見つけていただけるとても嬉しいです。
- 団体の活動をSNSでシェアする
- フードや毛布など物資を送る
- 月千円程度からの継続寄付を始めてみる
- 譲渡会やボランティアに参加してみる
- 周囲の人に保護動物のことを話してみる など
大きな行動でなくても構いません。関心を持つこと、声を届けること、小さな支援を続けること。その一歩が、動物たちの「福祉」を支える確かな力になっていくはずです。
そしてもしお時間があれば記事や白書を読んだ感想をアンケートに答えていただけると嬉しいです。
引用資料
1)日本動物福祉協会 (JAWS) 動物福祉について URL
2)厚生労働省 都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等(平成26年度~令和5年度)URL
犬猫保護団体 活動白書2025 調査概要 URL
調査対象: アマゾンジャパンの保護犬・保護猫支援プログラムに登録している犬猫保護176団体
※保護団体数・・・犬のみ保護:20団体、猫のみ保護:98団体、犬猫両方保護:58団体
保護頭数・・・全団体合計:14,523頭、1団体あたり中央値:34頭
調査期間: 2024年12月12日~29日
調査方法: オンライン調査
調査元: 公益社団法人アニマル・ドネーション
調査協力:アマゾンジャパン合同会社
 このテーマのゴール
このテーマのゴール


ゴール ALL
日本の動物福祉の向上を
日本の動物福祉の向上のため、AWGsでは法制度の整備、教育へのアプローチ、地域との連携など包括的に取り組み、すべての動物が安心して暮らせる社会基盤を築くことを目指します。